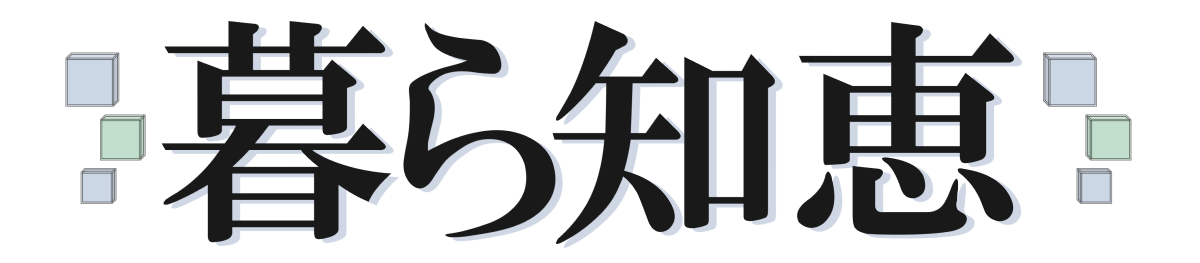常温での保存
おもちは日本では正月の料理として定番であり、中には正月に家庭で餅つきをする家もあるでしょう。
正月は餅料理を作って食べることが多いですが、正月過ぎるとお餅が余ることもあります。
はりきって作りすぎたようなお餅は、出来れば長く保存しておきたいものです。
餅は長持ちしないので保存方法を考えないとなりません。
おもちは市販のものは常温で保存しても構わないですが、ついた餅は常温で保存するとすぐにカビが生えます。
暗いところで保存してもカビは生えますので、出来れば冷蔵で保存した方が良いです。
どうしても常温で保存したい場合は、ボールに水を入れてそこにお餅を入れて冷暗所で保存しましょう。
水は毎日取り替える必要があります。
しかしながら、どのような方法を使ったとしても、常温での保存は短い期間に限られるでしょう。
ただしつきたての餅でも乾燥保存すれば長く常温で保存でき、作った餅を天日で干して乾燥させると長持ちします。
乾燥させるなら小さく薄く切った方が早く乾きます。
乾燥させた餅は、焼いたりして煎餅などにして食べると、風味が落ちず美味しくいただけます。
冷凍庫での保存
冷蔵庫で保存する場合も、この温度でもカビが生えやすいのであまり長くは保存できません。
長く保存するなら冷凍庫で凍らせて保存するしかないでしょう。
冷凍庫に餅を入れるときは、つきたてなら冷まして、餅を小分けにして、ラップなどで包んで密閉して空気が入らないようにして冷凍庫に入れます。
冷凍庫なら長いと3ヶ月は保存できます。
冷凍したおもちを食べるときは、解凍しないでそのまま焼いたり似たりして料理します。
その場合は、中まで火が通り凍った部分がないようにしてじっくりと料理しましょう。
解凍してから料理しても良いですが、解凍するなら自然解凍した方が風味が落ちません。
すぐに食べたいと言うときは電子レンジを使う方法もあります。
電子レンジで解凍するときは、ポイントとしてはお餅をいれた容器に水をお餅が隠れるぐらい入れて、そのままレンジにかけるという方法です。
そしてお餅が柔らかくなったら解凍終了です。
時間としては3分前後レンジにかければいいでしょう。
カビの生えた餅
餅は保存状態が悪いとすぐにカビが生えてしまいます。
しかし、カビの生えた餅でもカビの部分だけを取り除けば、食べられないことはないです。
ただしカビは餅の中の見えない部分にも根を張っていますので、食べるときは焼いたりして中まで火を通してから食べるべきでしょう。
カビの部分だけとって、そのまま食べるのは止めた方が良いです。
どうしてもそのままカビの部分だけとって食べたいと言う場合は、やはり自己責任となるでしょう。